隔月の20日までには「やすら樹」の原稿を提出しなければならないのに、今月は出版社からの依頼原稿が二稿、学会の抄録が二稿もあって、とても「やすら樹」まで手がまわらない。わずか三枚半の随想なのだが、頭の中は医学的な論理をひねくりまわしているために、どうも情緒的な随想的機能が低下している。「何を書けばよいか」が出てこない。そんな窮地を講演に行く途中の車の中で妻にもらすと「要するにテーマが出てこないわけだから、モチーフも見当たらないわけだ」と言う。「リンゴがポトリと落ちた」というモチーフ(題材)から万有引力の法則という宇宙の心理が大テーマとして導き出されたように、内観の真理を導き出すことはできないものかと思う。
 確かに、内観は自分の生活史をモチーフにして一定の角度から光を当てて、その光と影の部分を観察し続けることによって、心の中の真理を導き出す作業である。小説家が何人かの登場人物の織りなす人生模様をモチーフにして、人間の真実や人生の真理をテーマとして導き出そうとする芸術活動と同じ作業である。ただ「人間とは・・・」「人生とは・・・」とお説を並べても、少しも感動を伴わない。読み終わった時は頭から忘れてしまっている。論文調の学説ではイメージが生まれないし、心に残らない。ところが、小説は読む人の心を引きつける。それがテレビドラマや映画になればもっと強烈だ。
確かに、内観は自分の生活史をモチーフにして一定の角度から光を当てて、その光と影の部分を観察し続けることによって、心の中の真理を導き出す作業である。小説家が何人かの登場人物の織りなす人生模様をモチーフにして、人間の真実や人生の真理をテーマとして導き出そうとする芸術活動と同じ作業である。ただ「人間とは・・・」「人生とは・・・」とお説を並べても、少しも感動を伴わない。読み終わった時は頭から忘れてしまっている。論文調の学説ではイメージが生まれないし、心に残らない。ところが、小説は読む人の心を引きつける。それがテレビドラマや映画になればもっと強烈だ。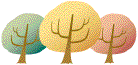 内観は、自分の心の中に「してもらったこと」のイメージが映像化されて出てくる。思い出している内観者は映画監督である。カメラをひいてみたり、クローズアップしてみたり、ぐるりと周囲にカメラを回してみるように指示をしながら「してもらったこと」の意味を探ろうとする。ライト係に指示して、光を静かに落としてみる。夕焼空が窓から見える。台所で炊事をしているお母さんの背中が見える。音響係に、カラスの鳴き声を入れてもらう。柱時計は五時三十分を指している。小学一年生の自分が、勝手口の戸を開いて「ただいまァ」と帰ってくる。かじかんだ手をこすりあわせながら膝小僧も真っ黒けで、頬は真っ赤だ。「ああ寒かったでしょう。お風呂に入りなさい。身体をよく洗いなさいよ」若いお母さんの顔がふっくらと笑っている。しばらくすると、お風呂場の方から大きな声で「夕焼けこやけで日がくれてーェ」と自分の歌声が聞こえてくる。ジーンと痺れるように暖まる手足の感覚が蘇ってくる。焼魚の焼ける匂いがプーンと鼻にしみ入る。
内観は、自分の心の中に「してもらったこと」のイメージが映像化されて出てくる。思い出している内観者は映画監督である。カメラをひいてみたり、クローズアップしてみたり、ぐるりと周囲にカメラを回してみるように指示をしながら「してもらったこと」の意味を探ろうとする。ライト係に指示して、光を静かに落としてみる。夕焼空が窓から見える。台所で炊事をしているお母さんの背中が見える。音響係に、カラスの鳴き声を入れてもらう。柱時計は五時三十分を指している。小学一年生の自分が、勝手口の戸を開いて「ただいまァ」と帰ってくる。かじかんだ手をこすりあわせながら膝小僧も真っ黒けで、頬は真っ赤だ。「ああ寒かったでしょう。お風呂に入りなさい。身体をよく洗いなさいよ」若いお母さんの顔がふっくらと笑っている。しばらくすると、お風呂場の方から大きな声で「夕焼けこやけで日がくれてーェ」と自分の歌声が聞こえてくる。ジーンと痺れるように暖まる手足の感覚が蘇ってくる。焼魚の焼ける匂いがプーンと鼻にしみ入る。 こうして書いていると内観は文学や音楽や美術を全てとり入れた総合芸術活動のようなもので、その底に流れる心の真理が内観者に強烈なインパクトを与えている。それは自分が自分自身のドラマに感動してのことである。しかし、単に日記のように一日の出来事を記録するような作業では芸術にならない。
こうして書いていると内観は文学や音楽や美術を全てとり入れた総合芸術活動のようなもので、その底に流れる心の真理が内観者に強烈なインパクトを与えている。それは自分が自分自身のドラマに感動してのことである。しかし、単に日記のように一日の出来事を記録するような作業では芸術にならない。 やはり内観の視点を一定にして、光の当て方カメラのアングル、登場人物のやり取りをきめ細かくリアルに描写するところに内観の芸術性が表現されてくるもののようだ。
やはり内観の視点を一定にして、光の当て方カメラのアングル、登場人物のやり取りをきめ細かくリアルに描写するところに内観の芸術性が表現されてくるもののようだ。急に自動車のフロントガラスに雪がはじけ散った。景色が灰色にくすんで、道路が光って見える。外の世界は凍てついて見える。妻は小刻みにブレーキを踏みながら坂を下っていく。私は助手席にいて「やすら樹」の原稿のことを考えている。

