


あなた
腸や心臓が手術台で裸のまま震えている
はじめて大気に触れた驚き
あなたからは 遠いところで
ドクリ ドクリと動いている
あなたは
「あなた」と呼ばれる人なのか
腸の中に残された
あなたの好きな昆布や豆が
あなたより確かな影をもっている
腸は広い手術室に溢れだす
あなたは そこにいて
指先で動揺する
あなたの生命に気づいていない
 完成
完成
鳴り響く炎
土が燃え 水が燃え
引き出される窒から
素焼は乳白色に乾いて出る
骨壷は カランとしていた
第一頚椎を拾い上げる
ひびた大腿骨 ゆがんだ肋骨
ろくろを回して 形を整えるまで
何千回も 朝日が斜めに照らした
夕やけの光は弱く 闇に消えた
裸電球は隙間風に揺れ
大地が揺れ
地球は ろくろの上に
揺れながら回った
竹べらで 角を 削り
箸で指の骨をつまみ上げる
ふるえる指先は息を止める
なめらかな関節の曲線
頭蓋骨の豊かさ
陶芸師の目がうなずく
素焼の枯れた作品
鼻をつく線香
白木の箱に収め
奥深い棚に置く
完成の年月日が書いてある
裸電球は揺れない
影は垂直になる
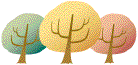 海賊船
海賊船
たくましい腕が潮に濡れる
童話の中から踊り出た海賊船
しぶきをあげて出帆する旗
いれずみは男たちのマーク
収穫を祝う唄声
ビヤダルの栓を抜くと
金・金・金
ビルの窓で燃えている
片目の船長がにやりと笑う
北をささない羅針盤の航路
有能な乗組員募集
男たちの体臭
背広姿の男たちが電車から降りて行く
骸骨の旗がネオンに光る
静かな出帆
 月
月
風が雲を引き摺って
闇は雲の下に移動する
ひからない明りがわたしを影にする
足もとから雲に被われる
闇がはびこり
動いてみせることもなく
裏がえしに寝返りを打っている
わたしの境界は 浮いて拡がる
無重力のこころが漂流する
クレーターは灰にうまり
舟は月面を離れる
港から遠ざかる
振る手は点になる
雲がたちこめる
河原の石をひっくり返せば
蟹が群がって出る
陰る月の下で
小さな闇に埋れていく
わたしの下から音が返ってくる
月の軌道を伝わって
闇に 水墨のうす明かりが振動する
そこに わたしの磁場が
犯されそうにぼんやりと見えはじめる
 雨
雨
舞い散る雨は
手のひらの上を ころげ落ちる
遠く薄い空が 生み落とした
ことばで
そぼそぼと語りかける
握りしめると はにかむように
指の間に 逃げ込んでしまう
だから そっと 母のように
両手を ふくらませて
受けとめてあげなければ
見上げると 遠く
手を伸ばせば 指に触れるあたりに
わたしであったものたちを
拾い集めるようにして
まだ遠のいてしまわぬうちに
空が乾き切ってしまわぬうちに
語りつくせる限りのものに
じっと耳をかたむけていよう
空はいつも ことば足らずのまま
雲をひきあげてしまうのだが
わたしの濡れた肩は 冷たい
ひとときの幻影のように
わたしは そぼ降る雨に濡れ
そこから 走り去ってしまいそうになる
もっと はっきりと
そこに わたしが立ち続けられるなら
形を整えた銅像のように
いつも いつまでも
最初から そこにあったもののように
さりげなく 全身を晒しておこう
夜が剥げ落ちるように
朝がめくれかえると
降り続いた雨に
光が濡れている
わたしは 眠りを被ったまま
わたしのままで いたにちがいない
雨は 水溜りをつくり
ゆっくりと消えて 乾こうとするのに
銅像ほどもない たるんだ肌が
わたしだと 信じ込むしかない形を
今朝も水溜りに映している
 いのち
いのち
貝塚に埋もれて 層に重なる
ことばの破片
掘り起こし 洗い流しても
つぎはぎだらけの お前の過去は
意味を土器にまで まとめ切れるか
手垢で鈍く光る曲線を撫ぜながら
女は赤茶けた土器に 子を宿す
女の胎盤は赤子に豊潤な血を流し込むが
無意味なことばを排除する
バリアをもっている
だから お前という人種は進化したのだ
隣の女の強情なことばに打ちのめされて
疲れ果てた女の乳を赤子に吸いとらせるが
赤子の脳髄は
無意味なことばを排除する
バリアを持っている
だから お前の赤子たちは まぎれもなく
人間に育ったのだ
女は傷ついた ひび割れから
漏れ出る涙を
なめし革にすわせ
赤く染みた指で
唇を濡らす
酔った男の背中は重い
うす汚れた男の指は
透けるほど白い女の内股を
見ている
外は 風
男は飲み続け
男は永遠に若く
いつまでも むずがる
明け方 一人の赤子が死んだ
土埃の中に 埋める
割れた土器のように
語ることさえしなかった
いのち
の意味を つなぎ合わせながら
いまだに形が歪過ぎる
あの赤子は何だったのか
お前と女の悲しみを背負って
黙りこくっている
深く 永い静寂
いまも女は そこに立っているのではないか
手向ける花を持って
白い骨壷を埋葬した墓石の前で
しなやかに
臨月の下腹部を撫ぜながら
そよ と吹く風は 髪を揺らし
若葉で 山が膨らんでいる
その日 突然
女は叫びながら「ノーモア・ヒロシマ」
ケロイドの赤子が
血を吹き出しながら
手足を震わせながら
キリキリ舞いをしながら
この世に生まれ出た
あれから 最早や
三千年の時間が過ぎようとしている
焼けただれたコンクリートの裂け目から
百足のような歩きをして
ゾロゾロと顔を出した虫たち
あいつはお前の顔によく似ていた
お前は はたして お前なのか
語ることばを持ちあわせない
永遠の静寂

| 所属の詩人協会 | 詩 集 |
|---|---|
| 鹿児島県詩人協会 | 鹿児島県詩集 |
| 日本現代詩人会 |