
出典:鹿児島県竹友断酒会機関誌「竹友」第15号号「咳をしてもひとり」
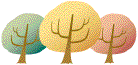
いま、私は縁側に坐って庭の垣根の山茶花の先の方に、小さな枯木が一本空を突き刺しているのを見ている。空は曇ったり晴れたり、時には雨を降らせたりするが、おそらく永遠に空はあるだろう。この枯木はもう乾いている。春になる頃には朽ち果てて、無くなるのであろうか。私がもし夏になるまで生きていることが出来るなら、そこにはまた違った風景を眺めているのかもしれない。おそらく、すでに枯木のことをすっかり忘れたふうでありながら、空には真白い入道雲を見ているのかもしれない。
あなたは、今何を見ていますか。そこには死んだもの、生きているもの、そしていつかは死んでいくもの、それから永遠で無限なものを見ているに違いありません。どうしてこんなにも異なったものが同じ視野の中にあるのでしょう。枯本も山茶花も空も、今はすべて私のためにしつらえてある風景だ。私だけが今ここで、そんな風景を見ているのだから。そして私は縁側で拍動している。私もきっと、いつかは死ぬに違いない。それは、まちがいの無いことだが、1986年1月1日、私はこの世でただ一つの生命を呼吸して生きている。あなたも、たった一つの生命を万物の中心に置いて生きているのであろう。
しかし、それはつかの間の歳月、この世はあなたのものである。
この水色の空を、今私は美しいと思って見ている。そして永遠にある筈の澄んだ空に憧れている。私も空になりたい。無限にじっとあんなふうでありたいと無性に自分がいとおしくなって、限り無く大切なもののように思えてくる。そして何よりもあなたを大切にしたいと思わずにはおれない。こんな思いも、つかの間の歳月の中に消え去ってしまうのだろうか。
小豆島でひとり息絶えた尾崎放哉は「せきをしてもひとり」という孤独な句を残している。肺結核で死んだのだが、現代医学の技術なら、もう少しくらいは長生き出来た筈である。もっともっと沢山の句を作っていたかもしれない。肺結核は完治していただろう。放哉は頑健な体でたくましく土を耕していたに違いない。咳ひとつしない。そんな風景があってもよい。それが確かに望ましいことなのだが。
その時、放哉は咳込んでいた。生きているための苦痛を耐えながら、喘ぎながら、この句を作った。もしも放哉がもっと多くの句を作ることができたとしても、この句に勝る作品を生み出せただろうか。冬の夜は、隙間風がどんなにも冷たかったであろう。背中を摩ってくれる人もなく、ただひとり「せきをしてもひとり」であった。この一行の句が残り続ける不思議さの傍らには、うすい布団があり、湯呑があり、蟻が放哉の足もとを通り過ぎて、窓の外には海があって、海は静まりかえって、空がすっぽり包み込んでいる風景がおし黙って潜んでいる。
みんな、みんな一緒に連れだっていたのだ。その時、放哉の友人たちも、見も知らぬ小豆島の人々も一緒になって、空に包まれていたのだった。なんと美しい小豆島ではないか。こうして眺めている私の風景と同じように美しい。そして、今、私もひとり縁側に坐っている。空はいつもすぐそこで、手に届きそうなところにあって、徴妙に色を変えながら、私や私の心を包み込んでいる。私は包まれている。この無限で永遠な空の中で、一つの風景になって坐っている。あの枯木も山茶花も、そしてあなたも私も、みんな一つになって楽しげに、そこにあるではないか。死んだものも死ぬものも永遠なものと溶けあって、今、はっきりと、そして永遠に残り続けるにちがいない風景ではないか。

出典:鹿児島県竹友断酒会機関誌「竹友」第15号号「咳をしてもひとり」